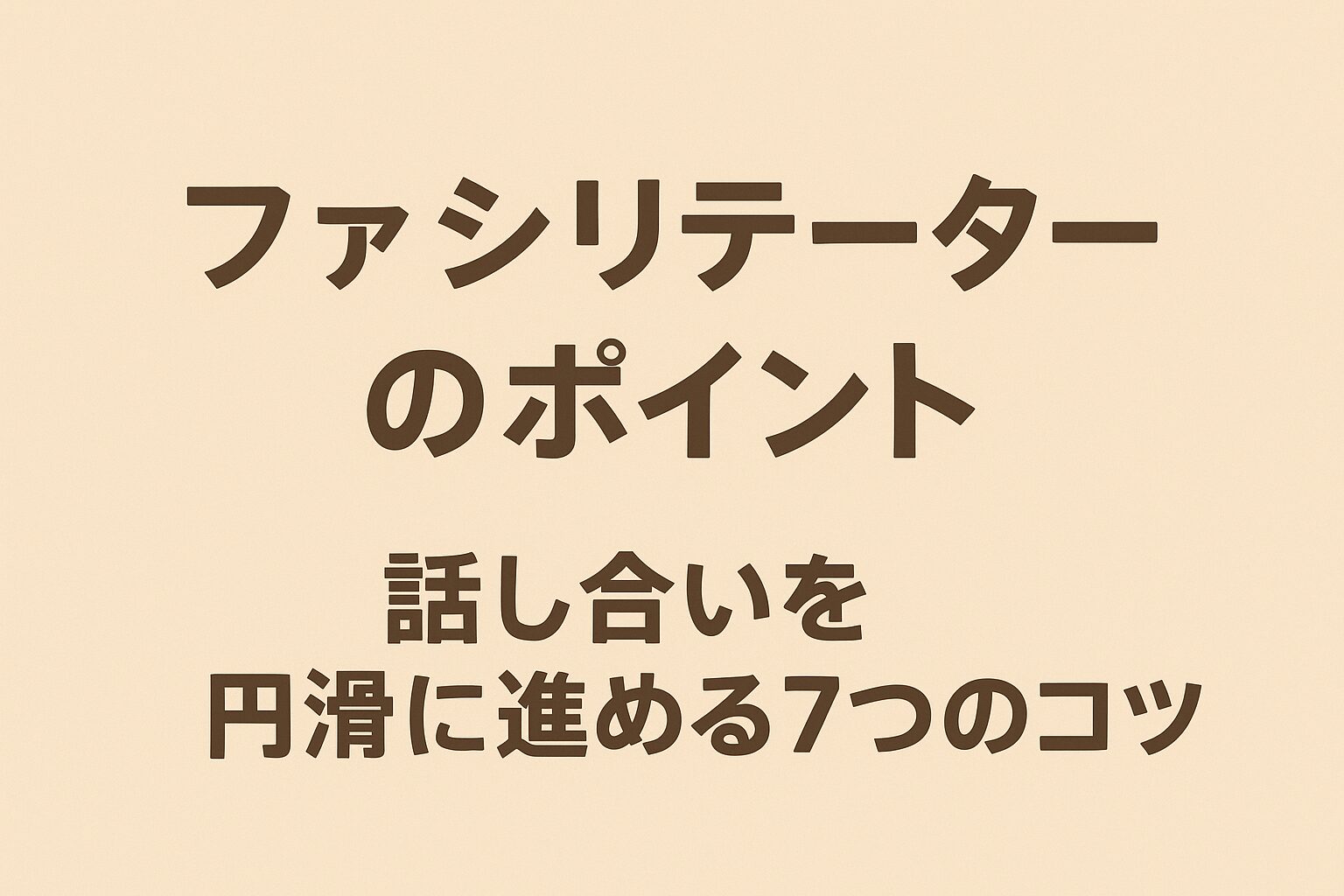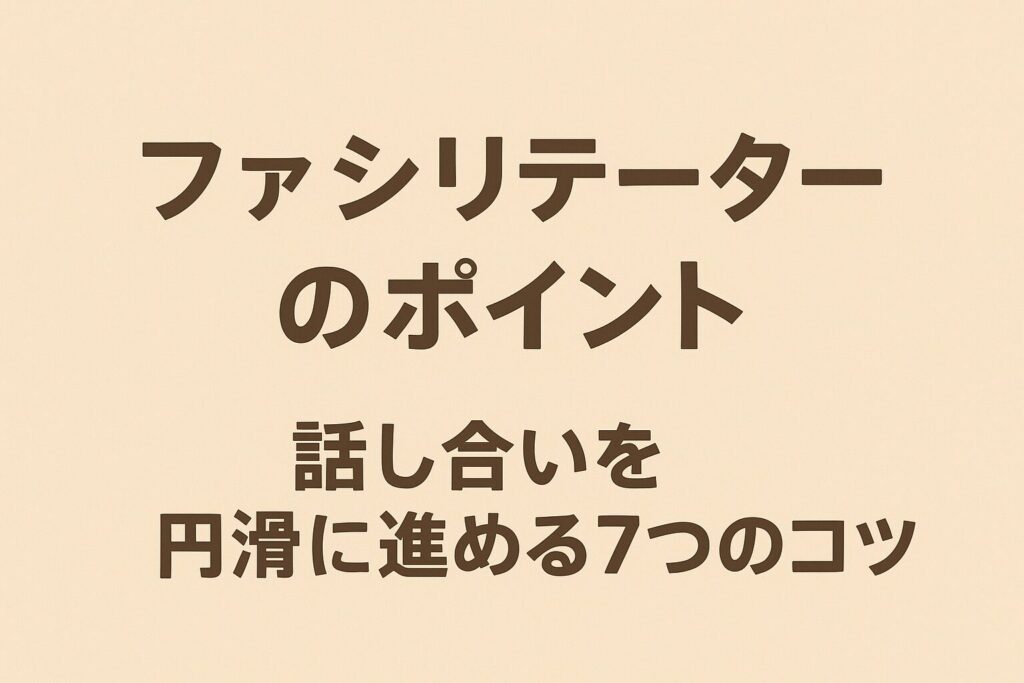
ファシリテーターとは?
ファシリテーター(Facilitator)とは、会議や打ち合わせ、グループワークなどで、
参加者が意見を出しやすく、円滑にコミュニケーションできるよう支援する役割を持つ人のことです。
特に福祉現場では、職員間の連携や多職種の意見調整において、
ファシリテーションスキルが求められます。
ファシリテーターの基本的な役割
- 話し合いの目的を明確にする
- 意見を引き出し、整理する
- 対立を調整し、合意形成をサポートする
- 全員が参加できる環境をつくる
ファシリテーターは「進行役」だけでなく、人と人をつなぐ橋渡し役でもあります。
ファシリテーターの7つのポイント
1. 中立的な立場を保つ
自分の意見や感情を持ち込みすぎず、どの意見にも公平に接することが大切です。
偏りがあると、参加者が発言しにくくなり、議論が停滞します。
2. 目的とゴールを明確にする
会議の冒頭で、「今日の目的」「ゴール(決めたいこと)」を明示しましょう。
目的が明確であれば、脱線しても軌道修正しやすくなります。
3. 全員が参加できる雰囲気をつくる
発言が少ない人には、「○○さんはどう思いますか?」と優しく促すことがポイントです。
安心して発言できる場づくりが、活発な議論につながります。
4. 話の整理と見える化を行う
ホワイトボードや付箋を使って、出てきた意見を「見える化」します。
意見の流れや関係性を整理することで、共通理解が生まれます。
5. 感情の流れを読み取る
言葉だけでなく、表情や声のトーンなどにも注目します。
感情的な対立が起きそうな場合は、一度立ち止まって整理する勇気も大切です。
6. 時間管理を意識する
各テーマにかける時間を意識し、話が長引かないように調整します。
終了前には「まとめ」と「次回への課題」を共有しましょう。
7. 合意形成をサポートする
多数決よりも、全員が納得できる形を目指すのが理想です。
「一部合意」や「持ち越し」など柔軟な対応も有効です。
福祉現場でのファシリテーションの実践例
| シーン | ファシリテーターの工夫 |
|---|---|
| 職員ミーティング | 感情的な対立を防ぎ、利用者支援に焦点を戻す |
| ケース検討会 | 多職種の意見を整理して支援方針を共有する |
| 研修・勉強会 | 参加者が自ら考え、意見を出し合えるよう促す |
福祉現場では、上下関係や専門職の違いがあるため、話し合いの「安心感」づくりが重要です。
まとめ:話し合いを支える「聞く力」と「つなぐ力」
ファシリテーターは、話し合いを単に進行する人ではなく、

おのぴの
人と人をつなぎ、チームの力を引き出す存在です。
福祉現場でもこのスキルを活かすことで、
より良い支援や職場の協働を実現することができます。