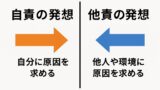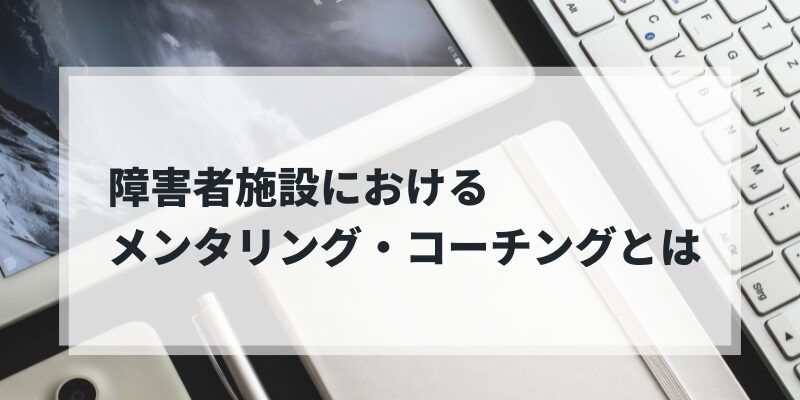
障害者施設では、職員の成長やチームの連携を高めるために「メンタリング」や「コーチング」の考え方が注目されています。
どちらも「人を育てる支援」の方法ですが、目的や関わり方に違いがあります。
メンタリングとは?
メンタリングとは、経験のある先輩職員(メンター)が、後輩や若手職員(メンティー)を支援・指導する仕組みです。
職場の人間関係、悩み、キャリア形成などを含め、包括的なサポートを行うのが特徴です。
メンタリングの目的
- 新人や若手職員の定着を支える
- 職場の安心感を高める
- 組織文化を伝承する
- 相互理解を深める
メンタリングの進め方
- 信頼関係を築く
まずは安心して話せる関係を作ることが大切です。 - 定期的な面談を実施
月1回などのペースで話し合い、悩みや目標を共有します。 - 成長の振り返り
「できるようになったこと」や「課題」を一緒に確認します。
コーチングとは?
コーチングは、相手の内面にある力を引き出し、自発的な行動を促す手法です。
メンターが「教える」のに対し、コーチングでは「問いかけて考えさせる」ことを重視します。
コーチングの目的
- 自己成長を促進する
- 問題解決力や判断力を養う
- チーム全体のパフォーマンス向上
コーチングの基本スキル
- 傾聴:相手の話を遮らず、関心を持って聴く
- 質問:気づきを促す質問を投げかける
- 承認:努力や変化を言葉で認める
メンタリングとコーチングの違い
| 項目 | メンタリング | コーチング |
|---|---|---|
| 主な目的 | 支援・育成 | 自立・成長促進 |
| 関係性 | 先輩・後輩の関係 | 対等なパートナー関係 |
| 手法 | 経験を伝える | 質問で導く |
| 支援範囲 | 感情・キャリア含む広範囲 | 目標達成に焦点を当てる |
障害者施設での活用ポイント
障害者施設では、利用者支援と同じくらい職員育成の仕組みが重要です。
メンタリング・コーチングを導入することで、次のような効果が期待できます。
1. 職員の離職防止
メンターが新人を支えることで、孤立や不安を防ぎ、定着率が向上します。
2. チームのコミュニケーション向上
コーチングの質問型対話を取り入れることで、対話の質が高まり、意見交換が活発になります。
3. 支援の質の向上
職員の自己理解や成長が、利用者への支援にも良い影響を与えます。
導入のコツ
- 施設内にメンター制度を設け、OJTと連携させる
- 定期的なコーチング研修を実施する
- 面談記録やフィードバックを仕組み化する
まとめ
障害者施設でのメンタリング・コーチングは、「人を育てる文化」を作る大切な仕組みです。
単なる技法ではなく、信頼・対話・成長を重視した関わりが、施設全体の力を高めることにつながります。