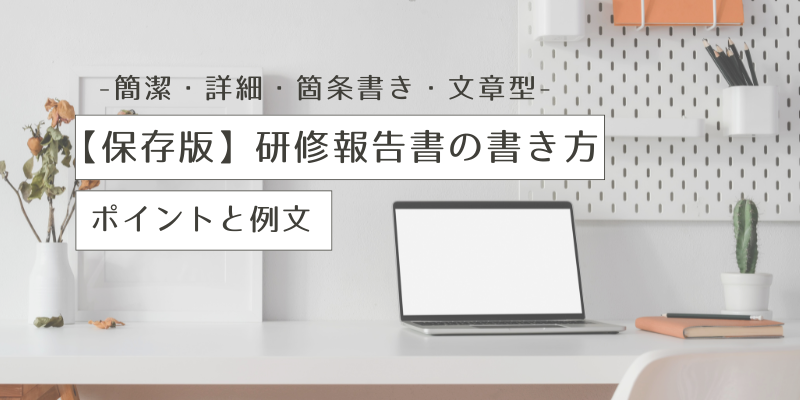
研修に参加した後、多くの方が悩むのが「研修報告書の書き方」です。
上司や人事に提出する報告書は、ただの感想文ではなく「学びを整理し、今後の業務にどう活かすか」を伝えることが重要です。
本記事では、研修報告書の基本構成や書き方のポイントを解説し、さらに 短め・長め・箇条書き・文章型の例文4種類 を紹介します。
この記事を読めば、自分に合ったフォーマットで分かりやすく効果的な研修報告書を書けるようになります。
研修報告書とは?
研修報告書とは、受講した研修の内容を整理し、学んだことや今後の活用方法をまとめる文書です。
提出先は上司や人事担当者であることが多く、研修の効果を職場に還元する大切な役割を持ちます。
研修報告書の基本構成
研修報告書には、以下のような基本的な構成があります。
① 表題・基本情報
- 研修名(例:「○○研修報告書」)
- 研修日程・場所(オンラインならその旨)
- 参加者氏名・所属
② 研修の概要
- 研修の目的
- 講師・主なプログラム内容
- 配布資料やワークの有無
③ 学んだ内容の要約
- 講義で特に印象に残った点
- 自分の理解を整理して簡潔にまとめる
- 専門用語はできるだけ噛み砕いて書く
④ 自分の気づき・学び
- 「なるほどと思ったこと」「新しく知ったこと」
- 「今までの支援や業務で気づかなかった点」
- 個人的に印象に残ったエピソード
⑤ 今後の活かし方
- 自分の業務や支援でどう応用できるか
- 実際に試してみたい方法や工夫
- チームで共有したい内容
⑥ まとめ
- 学びを一文で要約する(例:「利用者との信頼関係は日々の小さな積み重ねが大切だと再認識しました」など)
研修報告書の書き方のポイント
1. 客観的かつ簡潔にまとめる
研修内容は事実と感想を分けて記載。簡潔に要約することで読みやすさが増します。
2. 読み手を意識する
上司や人事が「実務でどう役立つか」を見たいケースが多いため、現場での活用や改善点に触れることが大切です。
3. 学びを今後に活かす視点を持つ
「研修で学んだ知識をどの業務にどう活かすか」を書くと、具体性が出て評価されやすくなります。
4. 形式を整える
箇条書きを使ったり、段落を分けたりして、読みやすいレイアウトを意識しましょう。
簡単な例文(抜粋)
研修名:「強度行動障害支援研修」
日時:2025年9月20日
場所:○○市福祉会館
概要:
強度行動障害のある方への支援方法について、基礎的な知識と事例を学んだ。講師からは「環境調整とチーム支援の重要性」が繰り返し強調された。
学んだこと・気づき:
- 行動の背景には必ず理由があることを改めて理解した。
- 利用者本人だけでなく、支援者の関わり方や施設の環境が影響することが大きい。
- 自分自身が「関わりやすさ」を優先してしまう場面があると気づいた。
今後の活かし方:
- 日々の記録を「行動の背景を探る視点」で整理していく。
- チームで支援方法を検討する場を設け、共有を意識する。
まとめ:
「利用者の行動の背景を理解し、環境調整を行うことが安定した支援につながる」と実感した。

こうした形で「学んだこと」と「活かし方」を両輪で書くと、報告書として評価されやすくなります。
研修報告書の例文(書き分け)
短めの研修報告書例(簡潔型)
研修名:「強度行動障害支援研修」
日時:2025年9月20日
場所:○○市福祉会館
概要:
強度行動障害のある方への支援について、基礎的な知識と事例を学んだ。
学びと気づき:
行動の背景には必ず理由があり、環境調整とチーム支援が大切だと再確認した。
今後の活用:
利用者の行動記録を背景に注目して整理し、チームで共有していきたい。
まとめ:
日々の支援を「行動の背景を理解する姿勢」で取り組んでいく。
・上司や同僚に手早く共有する「要点まとめ用」に適しています。
簡単な口頭での報告であれば

「○月○日に実施された○○研修に参加しました。業務に役立つ知識や事例を学び、今後の業務改善に活かしていきたいと考えています。」
と伝えることができます。
長めの研修報告書例(詳細型)
研修名:「強度行動障害支援研修」
日時:2025年9月20日
場所:○○市福祉会館
概要:
本研修では、強度行動障害のある方への支援方法をテーマに、講師による講義とグループワークが行われた。特に「行動の背景を理解し、環境調整を通じて安定した支援を行うこと」の重要性が繰り返し強調された。
学んだこと・気づき:
- 強度行動障害は「本人の特性だけでなく、周囲の環境や支援の仕方によっても強まる」ことを知った。(学び)
- 「支援者の都合で関わり方を決めてしまうと、かえって行動が悪化する可能性がある」という事例紹介が印象的だった。(学び)
- 自分自身も、忙しいときに「声かけを短縮する」など支援者目線の関わりをしてしまうことがあると気づいた。(反省)
今後の活かし方:
- 日々の記録を「行動の背景を探る視点」で書き直していく。
- 行動が出たときだけでなく、その前後の環境要因を意識的に確認する。
- チームでケース検討の時間を設け、共通理解を持った支援を進めたい。
まとめ:
今回の研修を通じて、強度行動障害支援は「本人理解」と「環境調整」「チーム支援」の3点が不可欠であると実感した。今後は日々の実践に学びを取り入れ、より安心できる生活環境を整えていきたい。
・こちらは研修内容をしっかり整理し、「学び」+「反省」+「今後の実践」を盛り込む形となっています。人事提出用や研修の記録として残すときに有効です。

「○月○日に○○研修に参加しました。研修では△△の基礎知識や実践事例を学び、特に□□に関する講義が印象に残りました。
今回得た学びを、日常業務に取り入れることで業務効率化やチーム力の向上につなげたいと考えています。
また、自身の課題であるコミュニケーションスキルについても、改善のヒントを得ることができました。今後は研修内容を実践に移し、成果を報告できるよう努めます。」

こんな報告ができるようになりたいね
箇条書きの研修報告書例(整理型)
研修名:「強度行動障害支援研修」
日時:2025年9月20日
場所:○○市福祉会館
概要
- 強度行動障害のある方への支援について学習
- 講師による事例紹介とグループワーク
学んだこと・気づき
- 行動の背景には必ず理由がある
- 環境調整やチーム支援の重要性を理解した
- 支援者の都合で関わりを決めると逆効果になる可能性がある
- 自分の支援を振り返ると、忙しさで声かけを省略してしまうことがある
今後の活用
- 行動記録を「背景の視点」で整理する
- 行動の前後にある環境要因を意識的に観察する
- チーム内でケース検討の場を設け、共通理解を図る
まとめ
- 「本人理解・環境調整・チーム支援」の3点を軸に実践を改善していく

こちらはすぐに要点が分かるので、上司やチームメンバーへの共有用に便利です。
文章型の研修報告書例(自然な文体)
研修名:「強度行動障害支援研修」
日時:2025年9月20日
場所:○○市福祉会館
今回の研修では、強度行動障害のある方への支援方法を中心に学びました。講師からは「行動の背景には必ず理由があり、それを理解することが安定した支援につながる」という点が強調され、グループワークを通じて具体的な事例を検討する機会もありました。
特に印象に残ったのは、「支援者の都合で関わり方を決めると、かえって行動が悪化する場合がある」という事例です。自分自身も、忙しいときに声かけを簡略化してしまうことがあり、それが利用者にとって負担になっている可能性があると気づきました。
今後は、行動の背景を探る視点を持ちながら日々の記録を整理し、行動の前後にある環境要因を丁寧に確認していきたいと思います。また、個人での気づきだけでなく、チーム全体でケースを共有し、支援方針を検討する場を増やすことも必要だと感じました。
今回の研修を通じて、強度行動障害の支援は「本人理解」「環境調整」「チーム支援」の3つが重要であると実感しました。これらを意識しながら、今後の実践に学びを活かしていきたいと思います。

読み手にじっくり伝える形式で、人事提出用や正式な研修記録に適しています。

「今回参加した○○研修では、△△や□□に関する知識を得ることができました。特に□□の事例は、自分の業務に直結する学びでした。今後は研修で得た知識を活かし、日々の業務改善に努めてまいります。」

上司としては、
- 〇〇の内容を聞いてきたよ~
- 〇〇の内容が勉強になったよ~
- 〇〇を△△して実践したいです~
って3つが入った報告が聞きたいわけです。その中でも△△は、内容を聞いて学んだことを「実践する形(職場への還元)」になるので、一番気になるポイントですね。
まとめ
研修報告書は「学びを整理する」だけでなく「職場への還元」を目的とする重要な文書です。
基本構成と書き方のポイントを押さえ、短め・長め・箇条書き・文章型など、状況に応じて書き分けることで、読み手に伝わりやすい報告書が作成できます。






