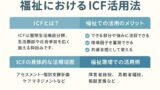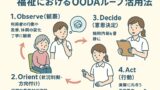KJ法とは?
KJ法は、文化人類学者・川喜田二郎氏が考案した情報整理と発想法です。
さまざまな意見やデータをカードや付箋に書き出し、グループ化・構造化して全体像を把握することで、課題の本質や新たな解決策を見つけることができます。

おのぴの
福祉現場では、利用者支援やチーム会議、地域福祉計画の場面で非常に有効な手法です。
福祉におけるKJ法の活用場面
ケース会議での情報整理
- 利用者の生活状況や課題、強みを職員が書き出す
- 似た意見や情報をグループ化し、支援の優先順位を明確化
- 多職種間での認識のズレを減らす効果が期待できる
支援計画の作成
- 本人や家族の要望、困りごと、将来の希望をカード化
- 「できていること」「課題」「希望」に分類
- 支援目標の具体化に役立つ
研修・振り返り
- 研修後の気づきや感想をKJ法で整理
- 「学んだこと」「現場で活かせること」「疑問点」にまとめる
- 職員同士の学びの共有がしやすくなる
地域福祉計画づくり
- 住民や関係者から出た意見をカードに書き出す
- 「ニーズ」「資源」「課題」にグループ化
- 地域全体の課題を見える化し、合意形成につなげられる
KJ法を活用するメリット(福祉現場の効果)
- 視覚化による情報共有のしやすさ
- 発言が苦手な人でもカードに書くことで意見を出しやすい
- 利用者・家族・職員など多様な視点を整理できる
- チームでの合意形成や支援方針の共有がスムーズになる
福祉現場でのKJ法 実践ステップ
1. テーマを決める
例:「利用者Aさんの生活支援の課題」
2. 情報を出す
付箋やカードに1つずつ書き出す
3. 似ているものをまとめる
共通点を見つけてグループ化
4. グループに名前をつける
例:「生活リズムの乱れ」「社会参加の希望」
5. 全体像を図解化
支援の方向性や優先課題を見える化
6. 支援計画や改善案に落とし込む
実際の支援や取り組みに反映させる
まとめ
福祉現場におけるKJ法は、 バラバラの情報を整理して見える化し、合意形成を助ける ための強力なツールです。

おのぴの
特にケース会議や支援計画づくりにおいて、チーム全体で方向性を共有するのに役立ちます。