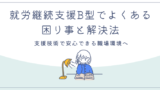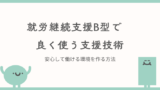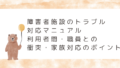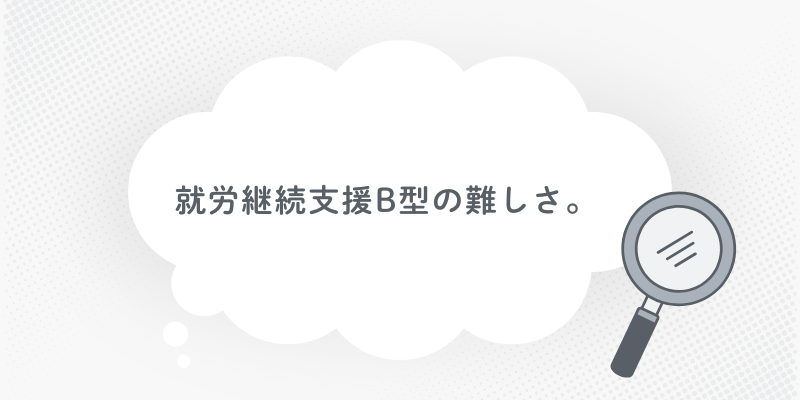
就労継続支援B型は、障害のある方が「雇用契約を結ばずに」比較的柔軟な形で働くことができる場ですが、運営側・利用者側それぞれに難しさがあります。整理すると以下のようになります。
1. 利用者側の難しさ
- 体調や精神状態の波
障害特性により、日によって作業への集中度や出勤率に差が出やすい。安定して働くのが難しい。 - 収入の低さ
工賃は全国平均で月1~2万円程度と低く、生活費の大部分は年金や福祉給付に依存せざるを得ない。 - 作業の単調さ
内職や軽作業が中心になることが多く、やりがいや成長実感が得にくい場合がある。 - 社会的孤立のリスク
一般就労とのつながりが弱いため、社会参加の幅が広がりにくい。
2. 事業所側の難しさ
- 収益性の確保
作業の単価が低いため、工賃アップのために仕事を獲得するのが難しい。 - 支援と生産性の両立
利用者に合わせた支援を行いながら、一定の品質・納期を守る必要がある。 - 人材確保の困難さ
支援員やサービス管理責任者の人材不足が全国的に深刻。 - 加算の条件が厳しい
工賃向上や人員体制などの要件を満たさないと収益に直結する加算が取れない。 - 地域性の影響
地域によっては仕事を依頼してくれる企業が少なく、事業所が存続しにくい。
3. 社会全体の難しさ
- 工賃と最低賃金の格差
「働く=生活できる」につながりにくく、障害者の経済的自立が進みにくい。 - 一般就労への移行率の低さ
A型や一般企業に移る利用者はごく少数で、出口戦略が弱い。 - 社会理解の不足
障害者の働き方について理解が広まっておらず、企業側も「仕事を任せられるのか」と不安を持ちやすい。
まとめ
B型は「働くことの機会提供」と「生活リズムの安定」には大きな役割を果たしますが、“働いて生活する” という社会的な当たり前を実現するには難しさが多い制度だといえます。
就労継続B型の「難しさ」を乗り越える工夫
1. 利用者側の工夫
- 体調管理のサポート
→ 無理のないシフト(短時間勤務、週2〜3回スタート)から始めて少しずつ増やす。 - 作業の見える化
→ 工程を細かく区切ったり、写真・イラストで手順を示すことで安心して取り組める。 - やりがいの創出
→ 商品を「地域で販売」したり、「イベントでお客様から直接声をもらえる」ようにすることで達成感を感じやすい。 - 仲間との交流
→ 作業だけでなく、休憩時間に雑談やレクリエーションを取り入れて社会的孤立を防ぐ。 - 一般就労への小さなステップ
→ 「施設外就労」や「職場体験」など、地域の企業とつながるチャンスを作る。
2. 事業所側の工夫
- 多様な仕事の確保
→ 内職だけでなく、農業・清掃・カフェ運営・ハンドメイド製品など、利用者の特性に合った複数の仕事を用意する。 - 地域企業との連携
→ 「障害者雇用の前段階」として企業に協力を依頼し、請負作業や施設外就労の場を広げる。 - 工賃向上への工夫
→ ネット販売や自主製品のブランド化、クラウドソーシングの活用で収益を増やす。 - 人材育成・チーム支援
→ 支援員が1人で抱え込まないように、ミーティングやマニュアルでチーム体制を強化。 - 利用者の「強み発見」
→ 作業能力だけでなく「人とのやり取りが得意」「丁寧さが武器」など強みに注目し、役割分担に活かす。
3. 社会的な工夫(制度・地域)
- 地域理解の促進
→ 学校や企業に向けた啓発活動で、障害者が働く姿を知ってもらう。 - 行政の支援制度活用
→ 工賃向上計画加算、処遇改善加算などをフルに活用し、支援員と利用者双方の待遇改善につなげる。 - 企業との協働モデル
→ 「B型事業所+企業+自治体」で協力し、地域に根差した仕事(観光、農業、清掃など)を創出する。
まとめ
- 利用者にとっては「安心して参加できる環境づくり」
- 事業所にとっては「多様な仕事の確保と支援のチーム化」
- 社会全体にとっては「理解と協力の広がり」
が、B型の難しさを和らげるポイントです。
就労継続支援B型における工賃アップの具体的方法
1. 工賃アップの具体的な方法
(1)仕事の幅を広げる
- 自主製品の開発
→ クッキーやパン、アクセサリー、布製品、アート作品など。
→ デザイン性や品質を高めると単価を上げやすい。 - 地域ニーズを活かした仕事
→ 高齢化地域では「除草・清掃・買い物代行」、観光地では「お土産制作・販売」。 - IT・デジタル系作業
→ データ入力、封入作業、軽微なプログラミング、デザイン補助などクラウドソーシング活用。
(2)販売・流通の工夫
- ネット販売
→ BASE、minne、Creema などハンドメイド販売サイト。
→ SNSで発信してファンを獲得。 - 企業や店舗と連携
→ 地元スーパーや道の駅で販売してもらう。
→ カフェやベーカリーを直営して販売。
(3)付加価値を高める
- 「障害者の手作り」という強みを前面に出すのではなく、
→ 「おしゃれで買いたい商品」として品質を上げる。 - デザインやパッケージにこだわり、一般市場でも選ばれる商品に。
(4)制度活用
- 工賃向上計画加算
→ 計画を立てて実績を出すことで加算が得られる。 - 処遇改善加算
→ 職員待遇の改善を通じて定着率を上げ、安定した支援につなげる。
2. 成功事例
事例①:パン工房(北海道)
- 地域の人気カフェと提携し、B型事業所がパンを製造。
- カフェのブランド力とSNSで認知度が上がり、月30万以上の売上。
- 利用者の工賃が月平均3万円に。
事例②:清掃・除草サービス(愛知)
- 地元自治体と協定を結び、公園や公共施設の清掃を請け負う。
- 依頼が安定し、利用者の作業時間も確保できる。
- 工賃が全国平均の2倍以上に。
事例③:アート作品販売(関西)
- 利用者の描いた絵をグッズ化(トートバッグ・ポストカード)。
- ネット販売とイベント出展でファンを獲得。
- 障害特性を強みに変えた成功例。
事例④:農福連携(九州)
- 農家と提携し、野菜の栽培から販売までを担う。
- 「地産地消」や「無農薬野菜」といった付加価値で高価格帯に。
- 地域企業からの信頼も厚く、利用者の就労体験につながった。
3. ポイントのまとめ
- 「単価の高い仕事」を獲得することが工賃アップの鍵。
- 地域・企業とつながることで安定的な仕事を得られる。
- 利用者の強みを商品やサービスに活かすことで独自性が出る。
B型事業所 工賃アップ実践リスト
1. 今ある仕事を工夫して単価を上げる
- 品質を揃える
→ 検品マニュアルを作って「バラつき」を減らす。 - パッケージの工夫
→ ラベルや袋を工夫するだけで商品価値が上がり、販売価格を上げられる。 - 作業効率を見直す
→ 道具や配置を改善して1時間あたりの作業量をアップ。
2. 小さく始められる自主製品づくり
- お菓子・パンの製造販売(保健所の許可が必要だが人気が高い)
- 布小物・手芸品(ポーチ、エコバッグなど)
- リサイクル品(古布や端材を利用した製品でコスト削減)
- アート作品のグッズ化(ポストカード・カレンダーなど)
ポイント:いきなり多品種ではなく「一つの得意分野」を伸ばすと安定。
3. 販売チャネルを広げる
- 地域のマルシェ・イベント出店
→ 地元の人に直接アピールできる。 - 委託販売
→ 道の駅・スーパー・カフェに置いてもらう。 - ネット販売
→ BASE、minne、Creema などのハンドメイド通販サイト。 - SNS発信
→ 利用者が投稿を手伝う形で「PRの仕事」にもなる。
4. 企業・地域とのつながりを作る
- 地元企業からの下請け作業
→ 封入・検品・清掃・組み立てなど。 - 自治体との連携
→ 公園の除草、資源回収、庁舎の清掃など安定的な仕事。 - 農家との協力(農福連携)
→ 収穫作業や出荷準備を請け負う。
5. 制度・加算を活用する
- 工賃向上計画加算
→ 目標と計画を立てて取り組むだけで加算が算定できる。 - 処遇改善加算
→ 職員の待遇を改善し、支援体制を強化する。 - 特定事業所加算
→ 人員配置や研修体制を整えて取得すれば報酬アップ。
6. すぐにできる小さなアクション
- 今ある作業の「見直し会議」を開く
- SNS用に「作業風景」や「商品写真」を撮って発信
- 地元のマルシェやイベントをリサーチ
- 利用者の「得意」を一人ずつメモして役割分担に活かす
- 地域企業に「お手伝いできることはありませんか」と相談してみる
まとめ
- 小さく始めて成功体験を積み重ねる
- 地域・企業との協力関係をつくる
- 制度をフル活用して事業所の体力を強くする
ことが「工賃アップ」につながる一番の近道です。