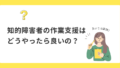障害者施設で保育士ができること
① 生活支援
- 身辺自立の支援
食事、着替え、排泄、歯磨きなど、子どもや利用者が自分でできるように促す。 - 生活リズムの安定
スケジュールを分かりやすく示し、安心して過ごせるように支援。 - 感情のコントロール支援
気持ちを言葉や行動で表現する練習、落ち着くための環境づくり。
② 発達支援・療育
- 遊びを通した発達支援
ブロック、粘土、音楽、体遊びなどで運動・認知・社会性を育てる。 - 感覚統合遊び
砂遊び、スイング、マット運動などで感覚過敏や鈍麻を調整。 - コミュニケーション支援
絵カードや視覚支援を使い、言葉が苦手な子の意思表示をサポート。
③ 集団活動の企画・運営
- 季節行事やイベント
七夕、ハロウィン、クリスマスなどの行事を企画して、施設の生活に彩りを与える。 - 音楽やリズム遊び
手遊び、リトミック、楽器あそびで情緒や協調性を育てる。 - 絵本や紙芝居の読み聞かせ
集中力や言葉の力、想像力を育てる。
④ 家族支援
- 子育て相談への対応
発達や生活習慣、遊び方についてアドバイス。 - 家庭との連携
連絡帳や面談で施設での様子を共有し、一貫した支援を行う。
⑤ チーム支援
- 多職種との連携
児童指導員、OT・PT・ST、看護師と連絡を取り合い、支援計画に反映。 - 職員へのアドバイス
子どもへの声かけ方法や遊びのアイデアを共有して支援の質を高める。
⑥ 安全管理
- 見守りと危険回避
転倒や誤食などの事故を防ぐための環境調整。 - 健康チェック
体調変化を早く気づき、必要に応じて看護師や家族に報告。
ポイント
保育士は「遊び」「発達」「安心できる関係づくり」のプロなので、
障害児や利用者の生活と心の安定に大きく貢献できます。
特に小さな子どもや、発達段階に応じた関わりが必要な利用者がいる施設では非常に重要な役割です。
① 保育士の役割の違い
| 施設の種類 | 主な対象 | 保育士の役割 |
|---|---|---|
| 放課後等デイサービス(児童向け) | 小学生〜高校生の障害児 | ・遊びや学習のサポート ・宿題の見守り、生活習慣の定着 ・集団活動の企画(運動遊び、工作、音楽) ・保護者への発達相談や家庭連携 |
| 児童発達支援(未就学児向け) | 0〜6歳(保育園・幼稚園に通う前の子も含む) | ・発達段階に応じた療育(遊びを通して成長を促す) ・感覚統合あそび、言葉の発達支援 ・集団生活への移行準備 ・保護者支援(家庭での関わり方アドバイス) |
| 生活介護(成人向け) | 18歳以上の障害者 | ・日中活動(創作、軽作業、音楽、体操)の企画 ・生活動作の介助(食事・排泄・着替え) ・感情の安定や人間関係づくりの支援 ・季節行事の企画運営 |
| 入所施設(グループホーム・施設入所支援) | 18歳以上の障害者 | ・起床〜就寝までの生活全般の支援 ・安心できる人間関係づくり ・趣味活動や余暇活動の提供 ・医療や福祉チームとの連携 |
| 医療型障害児入所施設 | 医療的ケアが必要な子ども | ・発達に合わせた遊び、スキンシップ ・看護師と協力して安全な支援 ・きょうだいや保護者への精神的サポート |
ポイント
- 児童向けでは「遊び・発達支援」が中心
- 成人向けでは「生活支援・余暇支援」が中心
- 保育士ならではの“子ども目線”の関わりが、どの施設でも生きます。
② 保育士がスキルアップできる研修・資格
| 分野 | おすすめ資格・研修 | ポイント |
|---|---|---|
| 発達支援 | 保育士等キャリアアップ研修(障害児保育) | 全国で受講可能。障害児保育に必要な基礎知識・実践を学べる。 |
| 発達支援 | 公認心理師補助資格、発達支援コーディネーター研修 | 保護者対応や支援計画作成に役立つ心理・発達の知識を強化。 |
| 感覚統合 | 感覚統合療法士(SI資格) | 作業療法士も学ぶ感覚統合の専門知識。遊びの幅が広がる。 |
| コミュニケーション | PECS(絵カード交換式コミュニケーション)研修 | 言葉が出にくい子へのコミュニケーション支援に有効。 |
| 福祉全般 | 強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践) | 行動が激しい子や利用者の支援スキルを上げられる。 |
| 福祉全般 | サービス管理責任者研修 | 将来、管理職を目指す場合に必要。 |
③ キャリアパス例
- 現場保育士 → 児童発達支援管理責任者 → 施設管理者
発達支援計画の作成やチームマネジメントができるようになり、キャリアアップ可能。 - 保育士 → 感覚統合療法・ABA療育の専門家
専門療育ができる保育士として価値が高まる。 - 保育士 → 相談支援専門員
家族や本人の相談にのる立場にキャリアチェンジも可能。
どの施設でも保育士の視点は重宝されます。
「遊び」「発達」「安心感づくり」をベースに支援できる人材は、福祉の現場でとても求められています。
児童向け施設(放課後等デイサービス・児童発達支援)で保育士ができる具体的な支援例を、1日の流れに沿って分かりやすく説明します。
児童向け施設での具体的な支援例
1. 受け入れ・来所
- 声かけ・安心させる関わり
- 「今日は〇〇をするよ」と見通しを伝えて不安を減らす
- 玄関で靴を揃える・手洗いなど身辺動作の習慣化
- 体調チェック
- 顔色や声のトーン、様子から体調や気持ちを確認
- 保護者からの引き継ぎを聞き取る
2. 宿題・個別課題
- 学習サポート
- 宿題を一緒にやる、集中できる環境を整える
- 難しい課題はステップを分けてサポート
- 個別療育
- ことばの練習(絵カード・しりとり)
- 手先を使う練習(ビーズ、はさみ、塗り絵)
- 数や形の理解を深める遊び
3. 自由遊び
- 感覚統合あそび
- ブランコ・トランポリン・マット運動で体を使う
- 粘土・スライム・砂遊びで感覚調整
- ごっこ遊び・コミュニケーション支援
- 人形遊びで社会性を学ぶ
- 順番を待つ練習や、友だちとのやりとりをサポート
4. 集団活動(メインプログラム)
- 運動遊び
- サーキット(跳び箱・平均台・マット)
- ボール遊びやリズム体操
- 創作活動
- 季節の工作(七夕飾り、ハロウィンマスク)
- お絵かき、コラージュ
- 音楽・リズム
- 手遊び歌、楽器あそび、リトミック
- 感情表現を引き出す音楽活動
- SST(ソーシャルスキルトレーニング)
- あいさつや順番待ち、断り方の練習
- 短いロールプレイで成功体験を作る
5. おやつ・休憩
- 食事動作の練習
- 手洗い、配膳、片付け
- 箸・スプーンの持ち方、座って食べる習慣
- 感覚過敏への配慮
- 苦手な食感・匂いへの対応
- 落ち着ける席に案内
6. 片付け・帰りの会
- 片付け習慣
- 「次に使う人のためにきれいにする」経験
- 遊んだものを一緒に片付ける
- 帰りの会
- 今日できたことを振り返る
- 明日の予定を伝え、見通しを持たせる
7. 送迎・引き渡し
- 保護者へのフィードバック
- 今日の様子・できたこと・困ったことを簡潔に伝える
- 家庭での関わり方や工夫の提案
保育士が特に活かせるポイント
- 遊びを通した支援
遊びを「療育の場」に変えられる専門性 - 子ども目線の声かけ
安心感を与え、やる気を引き出せる - 集団活動の企画力
運動・工作・音楽など、子どもが楽しめるプログラムを作れる - 保護者支援
家庭での接し方や遊び方をアドバイスできる
児童向け施設では、「楽しい!」「できた!」を積み重ねることがとても大事です。
保育士は、子どもの気持ちに寄り添いながら成長を支える役割を担います。
保育士が得意な「遊び」を、発達支援にしっかりつなげるためのアイデアをまとめます。発達の5領域(身体・認知・言語・社会性・情緒)に沿って整理すると実践しやすいです。
遊びを発達支援につなげるアイデア集
① 身体発達(粗大運動・微細運動)
| 目的 | 遊びの例 | 支援の工夫 |
|---|---|---|
| バランス感覚・体幹を育てる | サーキット遊び(平均台・マット・フープ)、トランポリン、リズム体操 | 難易度を調整し「できた!」を積み重ねる |
| 筋力・協調運動 | ボール遊び、けんけんぱ、綱引き、障害物競走 | 褒めるポイントを明確にする(キャッチできた、転ばず走れた) |
| 手先の器用さ | ビーズ通し、折り紙、洗濯ばさみ遊び、粘土 | 使う素材の硬さを調整、達成しやすいステップを設定 |
② 認知(知的発達)
| 目的 | 遊びの例 | 支援の工夫 |
|---|---|---|
| 数や形の理解 | 積み木、型はめパズル、数あそびカード、かるた | 「1つ、2つ…」と一緒に数える声かけ |
| 記憶力・注意力 | 神経衰弱、間違い探し、宝探しゲーム | ルールをシンプルにして成功体験を作る |
| 問題解決力 | ブロックで家を作る、迷路遊び | 「どうしたらできるかな?」と考える機会を作る |
③ 言語・コミュニケーション
| 目的 | 遊びの例 | 支援の工夫 |
|---|---|---|
| 言葉の獲得 | 絵カード遊び、しりとり、ままごと | モデル言語を繰り返し示し、真似しやすい言葉から |
| 会話の練習 | 人形劇、絵本の読み聞かせ、ロールプレイ | 「◯◯ちゃんはどう思う?」と気持ちを引き出す |
| 表現力 | 自由画、音楽に合わせて動く、ことばリズム遊び | 言葉が出ない子には動作やジェスチャーでもOKにする |
④ 社会性(対人関係)
| 目的 | 遊びの例 | 支援の工夫 |
|---|---|---|
| 順番を待つ | すごろく、順番ゲーム、ボーリング | 「次は誰かな?」と見通しを伝える |
| 協力・役割分担 | お店屋さんごっこ、協力して工作、リレー | 成功したら一緒に喜ぶ経験を積ませる |
| ルール理解 | フルーツバスケット、じゃんけん、椅子取りゲーム | 簡単なルールから始めて、徐々に複雑にする |
⑤ 情緒(感情調整)
| 目的 | 遊びの例 | 支援の工夫 |
|---|---|---|
| 気持ちの表現 | 感情カード、気持ち色ぬり(楽しい=黄色、怒り=赤) | 名前をつけて気持ちを言葉にする練習 |
| ストレス発散 | 大きな紙にお絵かき、風船バレー、新聞紙ちぎり | 感情を安全に発散できる場を確保 |
| 落ち着く練習 | 深呼吸ごっこ、ふわふわスカーフでリラックス、音楽鑑賞 | 落ち着きやすいBGMや照明で環境を調整 |
ポイント
- 遊びの「ねらい」を意識する
(例)「今日は協力して遊ぶ経験を積む」「順番を待つ練習をする」 - 難易度を調整
成功体験を積めるレベルから始め、少しずつ挑戦を増やす - 視覚支援を活用
絵カード・写真・ホワイトボードで見通しを持たせる - 振り返りを一緒にする
「今日は◯◯ができたね!」と自己肯定感を育てる