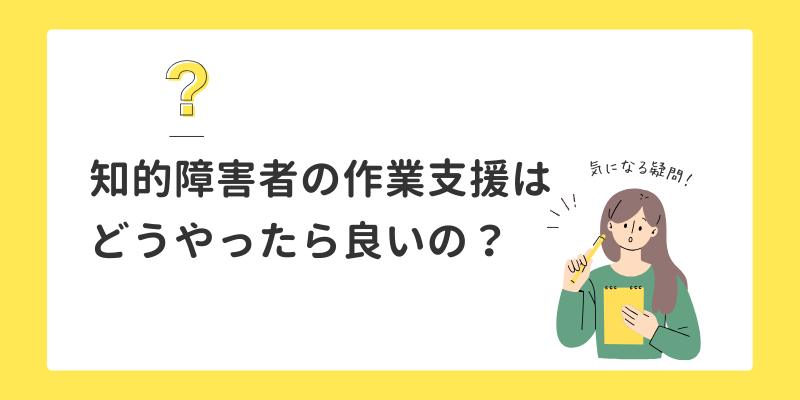
知的障害のある方への作業支援について説明します。
作業支援は「できることを伸ばし、自立を促す」と同時に「働くことを通じて生活のリズムや社会参加を支える」ことが目的になります。
① 作業支援の基本的な考え方
- 個別性の尊重:障害の程度や得意不得意、興味に応じた作業を設定する。
- 成功体験を重ねる:達成感や自信が持てるように、できる作業から始めて徐々にステップアップ。
- 安心できる環境:わかりやすい指示、整理された作業環境、失敗しても責めない雰囲気づくり。
- 社会性の育成:あいさつ、報告、相談など、作業を通して社会的スキルも学べるようにする。
② 支援の具体的方法
- 作業の手順化
- 作業を細分化し、順番をわかりやすくする。
- 写真やイラスト、チェックリストで視覚的に示す。
- 作業環境の工夫
- 道具や材料の置き場を固定する。
- 「次に何をするか」が一目でわかるように整理整頓。
- 声かけ・指示
- 短く、具体的に。例:「これを3つ箱に入れてください」
- 抽象的な指示は避ける(「きちんとやってね」より「まっすぐにそろえてね」)。
- 作業ペースの調整
- 疲れや集中力を考慮し、適度に休憩を入れる。
- 得意な作業と苦手な作業を組み合わせ、負担が偏らないようにする。
- 評価とフィードバック
- 良い点を具体的に褒める(例:「この箱、角がぴったりそろっていてきれいだね」)。
- 修正が必要なときは方法を一緒に確認する。
③ 主な作業の例
- 軽作業:箱折り、袋詰め、シール貼り
- 清掃:机拭き、掃き掃除、ゴミ分別
- 農作業:水やり、収穫、仕分け
- 調理補助:野菜の仕分け、食器拭き
- 工房作業:手芸品、陶芸、印刷など
④ 支援者のポイント
- 「できない」より「どうすればできるか」を一緒に考える
- 無理に急がせない(焦りは失敗や不安につながる)
- 利用者同士の協力を促す(「○○さんに聞いてみよう」など)
- 将来の就労や生活につながる視点で支援をする
「就労継続支援(A型・B型)の作業支援の違い」 と 「生活介護での日中活動としての作業支援」、さらに 「支援記録に書くときの観察ポイント」 を説明します。
① 就労継続支援(A型・B型)の作業支援
A型(雇用型)
- 特徴:利用者は事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上の給与が支払われる。
- 作業支援の視点
- 一般就労に近い形で「業務遂行力」「勤怠」「報連相(報告・連絡・相談)」を意識する。
- 支援者は「職場で求められる基準」を伝え、習得を支援する。
- 作業効率や正確性を高める練習が多い。
B型(非雇用型)
- 特徴:雇用契約は結ばず、工賃が支払われる(時給・出来高制が多い)。
- 作業支援の視点
- 個々のペースを尊重しながら作業を通じて「生活リズム」「作業習慣」を育てる。
- 得意分野を生かしやすく、成功体験を重ねやすい。
- 作業効率より「参加すること」「やり遂げること」を重視する。
② 生活介護での日中活動としての作業支援
- 目的:生産性よりも「生活の充実」「社会参加」「役割の実感」が中心。
- 作業例
- 簡単な内職(シール貼り、袋詰めなど)
- 園芸・清掃・調理補助などの日常生活につながる活動
- 手芸や創作活動(陶芸、絵画など)
- 支援のポイント
- 無理のない範囲で役割を持ち、「自分も貢献している」という感覚を大切にする。
- 作業の成果より「できた体験」や「楽しさ」を重視する。
- 体調や気分に応じて活動を柔軟に調整する。
③ 支援記録に書くときの観察ポイント
支援記録には「行動の事実」「本人の反応」「支援の工夫」を書くと役立ちます。
観察の視点例
- 作業面
- 指示を理解できたか(口頭、視覚支援など)
- 作業をどの程度自立してできたか
- 集中力や作業ペースはどうだったか
- 感情・態度面
- 楽しそうにしていたか、不安そうだったか
- 褒められたときの反応
- 他者との関わり(協力・会話など)
- 支援者の関わり
- どのような声かけ・工夫が有効だったか
- 支援により改善した点・課題が残った点
- 今後につながる視点
- 継続して取り組めそうな内容
- 次回はどの支援方法を試すか
まとめると、
- A型:就労に近い、成果・効率重視
- B型:生活リズム・作業習慣重視
- 生活介護:生活の充実、役割実感重視
- 記録:事実・本人の反応・支援の工夫を具体的に
次は、知的障害者の作業支援における「支援記録の書き方例」を説明します。
支援記録の書き方(作業支援)
1. 基本情報
- 日付:2025年〇月〇日
- 活動内容:例)袋詰め作業
- 時間:〇時〜〇時
2. 本人の様子(事実ベース)
- 作業開始時の表情や態度
例:「開始前は少し緊張した様子だったが、声かけにより着席した」 - 作業の理解度・遂行状況
例:「見本を示すと理解でき、自力で10個続けてできた」 - 集中力や体力面
例:「途中で手が止まる場面があり、5分ほど休憩をとった後は再開できた」
3. 本人の反応・気持ち
- 成功体験や失敗時の反応
例:「褒められると笑顔を見せ、自信を持って次の作業に取り組んだ」
例:「失敗すると肩を落とす様子が見られたが、再度説明すると取り組めた」 - 他者との関わり
例:「隣の利用者に『一緒にやろう』と声をかける場面があった」
4. 支援内容・工夫
- 指示や環境調整
例:「手順をイラストで示すことで理解がスムーズになった」 - 声かけやフォロー
例:「『あと5個で終わりです』と伝えると最後まで集中できた」
5. 評価・課題
- 良かった点
例:「自力で作業工程を繰り返せるようになった」 - 今後の課題
例:「集中力の持続に課題があり、休憩の取り方を工夫していきたい」
6. 次回への支援方針
- 例:「イラスト手順を継続しつつ、作業時間を少しずつ延ばし、達成感を積み重ねる」
書き方のポイント
- 「できた/できない」より「どのようにできたか」を具体的に
- 本人の感情や反応も記録する(「嬉しそうに」「落ち着いて」など)
- 支援者の工夫と効果を残す(次回の支援につなげやすい)
では、場面別(生活介護/就労継続支援B型)の支援記録の実際の記入例を整理します。
支援記録の記入例
① 生活介護での記録例
- 日付:2025年8月31日
- 活動内容:園芸活動(花の水やり)
本人の様子
開始時に少し落ち着かない様子があったが、スタッフがジョウロを手渡すと自ら花壇へ向かった。水をかけすぎる場面もあったが、見本を示すと加減を理解できた。
本人の反応
「きれいだね」と声をかけると笑顔を見せ、花を指さしながら喜ぶ様子があった。活動後も「またやる」と発言があり、楽しんで取り組んでいた。
支援内容・工夫
- 最初に見本を示し、視覚的に理解できるようにした。
- 水を入れすぎないように「このくらい」と声かけを行った。
評価・課題
楽しみながら活動に参加でき、役割意識を持つ様子があった。活動時間が短く、集中が続かなかった点が課題。
次回への方針
水やりを継続して担当し、活動時間を少しずつ延ばすことで達成感を積み重ねられるようにする。
② 就労継続支援B型での記録例
- 日付:2025年8月31日
- 活動内容:袋詰め作業
本人の様子
開始時に作業手順を確認すると、見本を見ながら自力で5回繰り返すことができた。その後、袋を持つ手が緩み、中身を落とす場面が見られた。
本人の反応
失敗した際に一瞬手を止めたが、スタッフが「大丈夫、もう一度やってみよう」と声をかけると再度取り組めた。完成品を渡すと笑顔で受け取り、達成感を示していた。
支援内容・工夫
- 作業台の上を整理し、必要な材料のみを置くようにした。
- 手順を口頭と身振りで具体的に説明した。
評価・課題
自力で作業工程を理解し、繰り返し行うことができた。袋を持つ力の加減に課題があり、今後は道具の工夫(台に固定するなど)も検討する必要がある。
次回への方針
同じ作業を繰り返し練習しつつ、完成数を記録して本人と一緒に確認し、達成感を強化する。
このように、
- 生活介護では「楽しさ・役割・生活の充実」に重点
- B型では「作業手順・習慣化・達成感」に重点
を置いて記録すると違いが明確になります。
では最後に、就労継続支援A型での支援記録の実際の記入例を整理します。
就労継続支援A型 支援記録例
- 日付:2025年8月31日
- 活動内容:商品の箱詰め作業(委託業務)
- 時間:10:00〜12:00
本人の様子(事実)
開始時刻前に着席し、作業開始の合図に合わせてすぐに取り組めた。
指示通り、商品を10個ずつ箱に詰め、20分間は集中して取り組んだ。
途中で数を間違える場面があったが、自ら「数が違います」と報告してやり直した。
本人の反応・気持ち
- 完成後に「終わりました」と声をかけることができ、報告の習慣が定着しつつある。
- 作業を終えた際、少し安心した表情を見せていた。
支援内容・工夫
- 作業開始前に「10個ずつ」という数量を再度確認した。
- 箱の横にカウント用の仕切りを置き、数えやすいように工夫した。
- 間違いに気づいたときに「自分で報告できて素晴らしいね」と即時にフィードバックした。
評価・課題
- 良かった点:
- 時間を守って作業に取り組む姿勢が安定してきている。
- 数の間違いを自己申告できた点は大きな成長。
- 課題:
- 集中が続くのは20分程度であり、それ以上は疲労により誤りが増える傾向。
次回への支援方針
- 作業時間を小分けに設定し、適度に休憩を挟むことで正確性を維持する。
- 報連相のスキル向上を目指し、「終了時に必ず報告」する習慣を継続的に支援する。
- 数量管理の正確性を高めるため、仕切りやカウンターの使用を続ける。
ポイント
- A型の記録は「就労に近い視点」→ 勤怠・作業遂行力・報連相 を重視。
- 評価には「一般就労につながるか」という観点を入れると効果的。
生活介護・就労継続支援B型・就労継続支援A型の支援記録例の違い を、実習や研修で使いやすいように 比較表 にまとめます。
作業支援における支援記録の比較表
| 項目 | 生活介護 | 就労継続支援B型 | 就労継続支援A型 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 生活の充実、役割実感、社会参加 | 作業習慣の定着、達成感の獲得 | 就労に近い経験、職業能力の向上 |
| 作業の特徴 | 創作活動、園芸、清掃など無理のない活動 | 袋詰め、内職など比較的簡易な作業 | 委託業務など精度・効率を求められる作業 |
| 支援の視点 | 「楽しむ」「役割を持つ」ことを重視 | 「繰り返し」「習慣化」「達成感」を重視 | 「勤怠」「作業遂行力」「報連相」を重視 |
| 本人の様子(記録例) | 花に水をやり、笑顔を見せた | 袋詰めを5回自力でできたが途中で手が緩んだ | 箱詰めを時間通り開始し、数の間違いを自ら報告した |
| 本人の反応(記録例) | 「またやる」と発言 | 失敗後も再挑戦し、完成時に笑顔 | 作業後に「終わりました」と報告、安心した表情 |
| 支援内容(記録例) | 見本を示し、声かけで加減を調整 | 作業台を整理し、口頭+身振りで指示 | 数量確認を徹底し、仕切りを使用、報告を促す |
| 評価・課題(記録例) | 活動を楽しめたが集中は短時間 | 工程は理解できるが持ち方に課題 | 勤怠・報告は安定、集中時間が短い |
| 次回への方針(記録例) | 活動時間を少し延ばし達成感を積む | 道具の工夫と回数記録で達成感を強化 | 作業を小分けにし、報連相を継続強化 |
まとめ
- 生活介護 → 「楽しさ・役割感」を中心に記録
- B型 → 「作業習慣・達成感」を中心に記録
- A型 → 「職業スキル・報連相」を中心に記録
では「まとめ」の部分に A型の視点 をしっかり追加して整理し直しますね。
まとめ(生活介護・B型・A型の記録の違い)
- 生活介護
→ 「楽しさ・安心感・役割感」を中心に記録する。
(例:笑顔・楽しそう・参加できたなど) - 就労継続支援B型
→ 「作業習慣・達成感・自分のペースでの遂行」を中心に記録する。
(例:繰り返しできた・完成数・工夫でできたなど) - 就労継続支援A型
→ 「就労に必要なスキル(勤怠・作業遂行力・報連相)」を中心に記録する。
(例:開始時間を守れた・間違いを報告できた・集中力の持続など)
つまり、
- 生活介護=生活の充実や役割を楽しめるか
- B型=作業習慣や達成感が育っているか
- A型=一般就労に必要なスキルが伸びているか
を意識して観察・記録すると、それぞれの目的に合った支援が見えるようになります。


