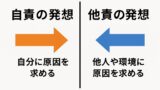ADHDとは「Attention Deficit Hyperactivity Disorder」の略で、日本語では「注意欠如・多動症」と呼ばれます。
主に、注意力の欠如・多動性・衝動性の3つの特徴を持つ発達障害の一つです。子どもから大人まで幅広い年齢層に見られ、生活や仕事、人間関係に影響を与えることがあります。
ADHDの主な特徴
集中力が続かない(不注意傾向)
・物事に集中しにくく、ミスや忘れ物が多い
・話を聞いていても注意がそれてしまう
・整理整頓や計画立てが苦手
落ち着きがない(多動傾向)
・じっとしていられず、動き回ってしまう
・授業中や会議中でも体を動かしてしまう
・話すスピードや声の大きさをコントロールしにくい
思いつきで行動する(衝動性)
・思ったことをすぐに口に出してしまう
・順番を待てない、感情のコントロールが苦手
・リスクを考えず行動することがある
ADHDの原因
ADHDの明確な原因はまだ完全には解明されていませんが、主に脳の働きや神経伝達物質のバランスが関係しているとされています。
また、遺伝的要因の影響も指摘されており、家族の中にADHD傾向を持つ人がいるケースも多いです。
ADHDの診断と支援
医療機関での診断
ADHDは医師(主に小児科、精神科、心療内科)による問診や観察、心理検査などを通じて診断されます。
子どもだけでなく、大人のADHD(成人期ADHD)も近年注目されています。
支援・対応のポイント
・見通しを持てるように予定を「見える化」する
・短時間で区切ったタスクを設定する
・叱責ではなく、成功体験を重ねるサポートを行う
・環境を整え、集中できる空間をつくる
学校・職場での配慮と支援
ADHDを持つ人は、環境や理解によって力を発揮できる場合が多くあります。
福祉・教育・職場での支援例は次の通りです。
学校での支援例
・座席を前方や静かな場所に配置する
・課題を小分けにして提示する
・個別支援計画を作成し、教職員間で共有する
職場での支援例
・仕事内容を明確に伝える
・定期的なフィードバックを行う
・スケジュール管理ツールを活用する
家族や周囲ができるサポート
ADHDを持つ人への理解と支援は、家庭や周囲の協力が欠かせません。
・「できない」ではなく「苦手」と理解する
・失敗を責めず、成功体験を積み重ねる
・専門家や支援機関に相談する
相談先の例
・発達支援センター
・児童発達支援事業所
・地域包括支援センター(成人期の場合)
・医療機関(精神科・発達外来など)
まとめ
ADHDは、脳の特性に基づく発達障害であり、本人の努力不足ではありません。
適切な理解と支援があれば、学校生活や社会生活の中で能力を発揮できるケースも多くあります。

周囲が温かく見守り、支援体制を整えることが大切です。