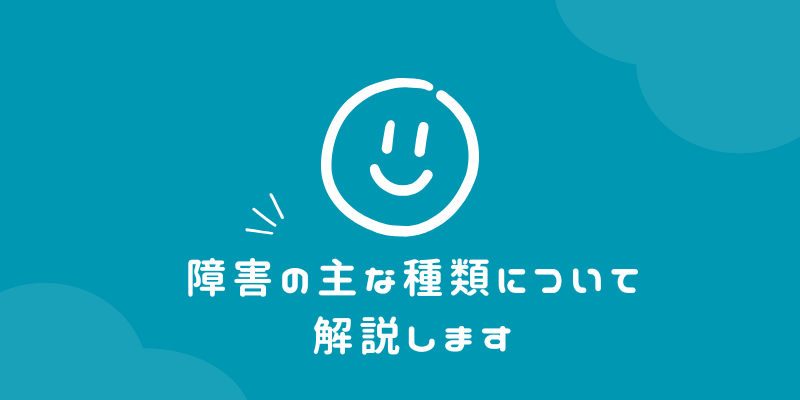
障害者施設には、利用される方の障害の種類や生活状況に応じていろいろな施設があります。そのため、まずは代表的な「障害の種類」を解説します。
障害の主な種類
身体障害
視覚障害(全盲、弱視など)
聴覚障害(ろう、難聴など)
肢体不自由(脳性麻痺、脊髄損傷、切断など)
内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、免疫、難病など)
知的障害
発達の遅れや学習面・社会生活面での困難
軽度から重度まで幅広く、支援の内容も多様
精神障害
統合失調症、うつ病、双極性障害など
社会生活や就労に困難を伴う場合が多い
発達障害
自閉スペクトラム症(ASD)
注意欠如・多動症(ADHD)
学習障害(LD)など
→ 知的障害を伴う場合と伴わない場合がある
障害者施設で対象となる分類
施設によって「対象」が決まっています。
生活介護施設:主に知的障害・重度身体障害
就労支援施設:知的障害・精神障害・発達障害など幅広く対象
グループホーム:自立生活が難しい障害者全般
医療型施設:身体障害や重症心身障害など、医療的ケアが必要な方
障害は大きく 身体・知的・精神・発達 の4つに分けられ、施設はそれぞれの障害特性や生活ニーズに合わせて役割分担している、というイメージです。「生活介護」と「就労支援」でどんな障害の人が多い?
では、「生活介護」と「就労支援」に分けて、どんな障害のある方が多いのか整理します。
障害者施設の利用者に多い障害の種類
生活介護(主に日中活動の支援)
対象者の特徴
・日常生活に常時介護が必要な人
・就労が難しい重度障害の人
多い障害の種類
知的障害(中度~重度)
身体障害(重度の肢体不自由、脳性麻痺、重度の内部障害など)
重症心身障害(重い身体障害と知的障害の両方を持つ人)
支援の内容
・食事や排泄、入浴などの介助
・創作活動、軽作業、リハビリ
・余暇支援や地域交流
就労支援(働くことをめざす支援)
対象者の特徴
・働く意欲はあるけれど、一般就労が難しい人
・訓練や支援を受ければ就労できる可能性がある人
多い障害の種類
知的障害(軽度~中度)
精神障害(うつ病、統合失調症、双極性障害など)
発達障害(ASD、ADHD、学習障害など)
身体障害(軽度で作業ができる人)
支援の内容
・作業訓練(内職、清掃、農作業、パソコンなど)
・就労に必要なスキル(時間管理、対人スキル)
・職場実習、就職活動支援
✨ ポイント生活介護 → 重度の障害があり「生活支援」が中心
就労支援 → 軽度~中度の障害で「働く支援」が中心
もし実習で行かれるのであれば、
「生活介護」では介助や余暇活動のサポート、
「就労支援」では作業の補助や声かけ、利用者のペースに合わせた支援が大切になってきます。
実習生としてそれぞれの施設でどう関わればいいか?
では、「生活介護」と「就労支援」それぞれで、実習生として意識したい関わり方について説明します。
実習生の関わり方
生活介護での関わり
基本姿勢
利用者さんの「できること」を尊重しながら、できない部分をサポート
スピードよりも安心・安全を優先
具体的な関わり方
食事や移動の介助 → 職員の指示をよく聞きながら丁寧に
創作活動やレクリエーションの補助 → 利用者さんが楽しめるように声かけ
コミュニケーション → 言葉だけでなく表情やしぐさも観察
生活リズムを大切に → 無理に活動をさせず、休憩のタイミングに配慮
ポイント
「安全・安心・尊重」の3つがキーワード
利用者さん一人ひとりのペースを見守る姿勢が大切
就労支援での関わり
基本姿勢
「働く体験」を支える意識を持ち、できることを伸ばす
支援というより「一緒に取り組む仲間」という姿勢
具体的な関わり方
作業補助 → ペースを合わせてサポート、難しいところはさりげなく手助け
就労訓練 → 時間管理やルールを一緒に確認、わかりやすく説明
声かけ → 頑張りを認めて「できたね」「いいね」とポジティブなフィードバック
休憩や切り替えのサポート → 気分の波がある方には柔軟に対応
ポイント
「できることを増やす」「自信を持ってもらう」ことが大事
褒める・認める・励ます を意識する
✨ 実習で大切な共通ポイント
職員の指示を最優先(安全や利用者理解のため)
記録(実習ノート)は「気づき」を素直に書く
「できた」「笑顔だった」「落ち着かなかった」など具体的な様子を残す
振り返りでは「なぜそうなったか」「次にどう関わるか」を考える
実習ノートに書ける「観察の視点リスト」や「振り返りの例文」
実習ノートを書くときに役立つ、利用者さんを観察するときの視点リストを「生活介護」と「就労支援」に分けてまとめます。
観察の視点リスト
共通の視点
表情 … 笑顔が多いか、緊張しているか、落ち着かない様子はあるか
コミュニケーション … 言葉・ジェスチャー・表情などでどのようにやりとりしているか
体調・行動 … 疲れやすい様子、休憩の取り方、動きにくさはあるか
周囲との関係 … 職員や他の利用者とどう関わっているか
安心しているか … 環境に馴染めているか、不安そうか
生活介護での視点
日常生活の様子
食事 … 自力で食べられるか、介助が必要か
移動 … 車椅子、杖、介助歩行など、どんな支援が必要か
排泄・着替え … どの程度自立しているか
活動への参加
創作・軽作業・レクリエーションにどのくらい関われるか
途中で疲れていないか、集中が続くか
感情の変化
好きな活動・苦手な活動で反応がどう違うか
就労支援での視点
作業の取り組み方
指示を理解して取り組めるか
どのくらい集中が続くか
作業スピードや正確さはどうか
コミュニケーション
職員に質問できるか
他の利用者と協力できるか
モチベーション
作業に意欲的か、途中でやめたくなるか
褒められたときや失敗したときの反応はどうか
自己管理
時間を守れるか
休憩を上手に取れるか
ポイント
「できること」と「難しいこと」を両方メモする
小さな変化や表情も観察して残す
「なぜそうなったのか?」を考えると振り返りに役立つ
観察視点をもとにした 実習ノートの書き方例(1日の記録例)
観察の視点をふまえて、実習ノート(1日の記録例) を「生活介護」と「就労支援」でそれぞれ書けるようにサンプルを見てみましょう。
実習ノートの書き方例
生活介護の例
日付:〇月〇日(〇曜日)
活動内容:午前…創作活動(塗り絵)、午後…散歩
観察したこと
Aさんは、塗り絵の活動で赤や青など好きな色を選んでいた。
クレヨンを持つときに手が震えていたため、職員が手を支えると安心した様子で最後まで取り組めた。
散歩では職員と手をつなぎ、笑顔が多く見られた。
自分の関わり
クレヨンを手渡す際に「次はどの色にしますか?」と声をかけると、少し考えてから選んでくれた。
散歩のとき「今日は風が気持ちいいですね」と声をかけると、にこっと笑ってうなずいてくれた。
振り返り
Aさんは「自分で選ぶこと」を大切にしていると感じた。
活動を急がせず、本人のペースで関わることが大切だと学んだ。
就労支援の例
日付:〇月〇日(〇曜日)
活動内容:午前…内職作業(袋詰め)、午後…清掃実習
観察したこと
Bさんは袋詰めの作業を開始後15分ほど集中して取り組んだが、途中から手が止まる様子が見られた。
職員が「あと5分頑張ろう」と声をかけると再び集中して作業を続けられた。
清掃実習では、雑巾がけを丁寧に行い、終わった後に「できました」と報告していた。
自分の関わり
作業が止まったときに「Bさんが並べた袋、とてもきれいですね」と声をかけると、表情が明るくなり再び取り組み始めた。
清掃中に「次はどこを拭きますか?」と確認すると、自分で考えて行動できた。
振り返り
Bさんは褒められることで意欲が高まると感じた。
次回は「作業の目標(時間や数)」を一緒に確認すると、達成感につながるのではないかと思った。
✨ 書き方のコツ1. 事実(観察)と自分の関わりを分けて書く
→ 主観と客観を区別するとわかりやすい
2. 具体的に書く
→ 「楽しそう」より「笑顔で拍手していた」と表現する
3. 振り返りは“気づき”を次につなげる
→ 「こうするともっとよかったかも」を残す





